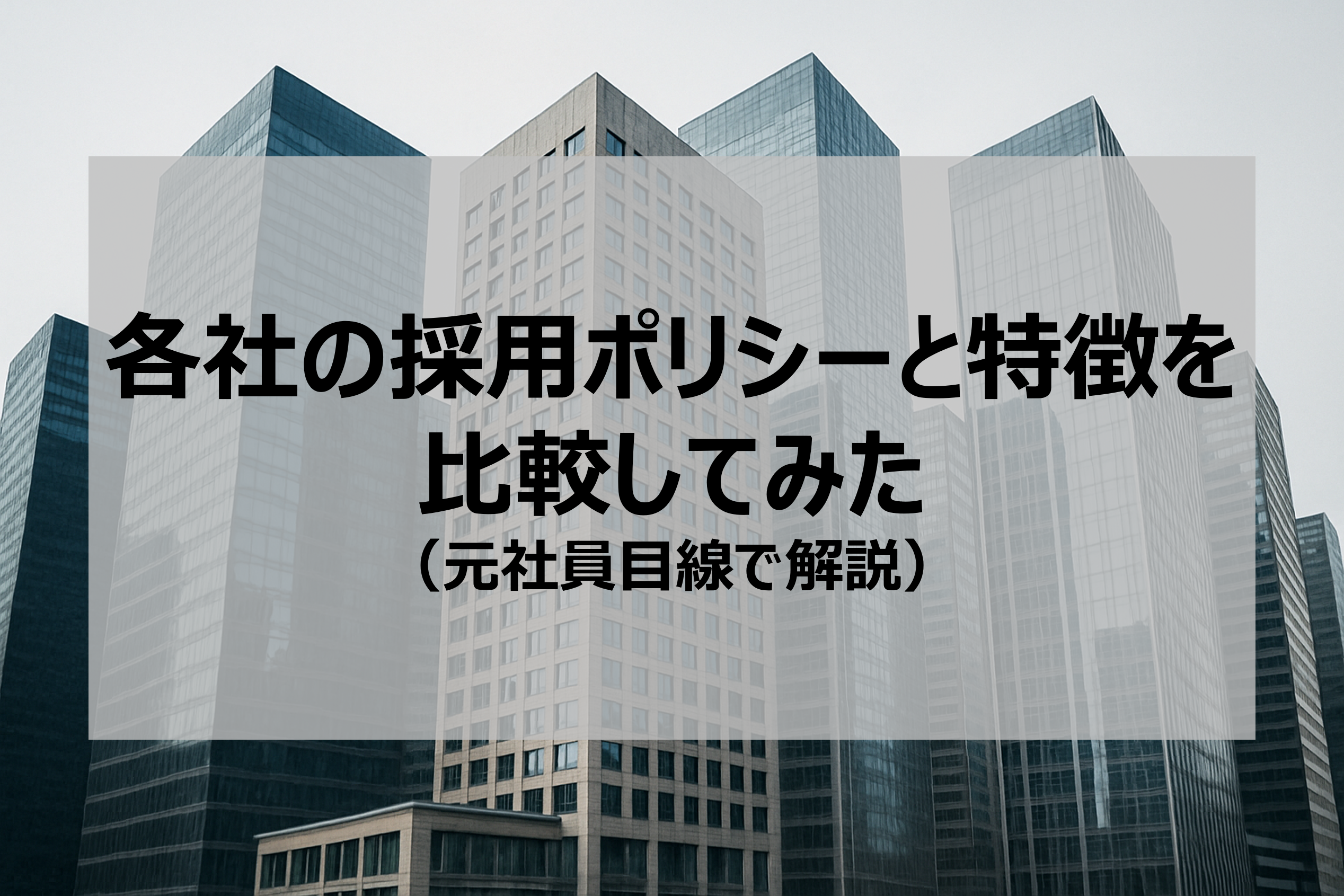次は「各社の採用ポリシーと特徴」ですね。就活生が一番気になるやつです!
だな。企業ごとに採用方式も異なる。”コンサル”で一括りにせず、自分が目指す企業に合った対策が必要になるな。
自分は就活時にMBB、ローランドベルガー、ATカーニー、BIG4、アクセンチュア、NRI、アビームを受けてきました。当時の自分の経験に加え、コンサルに就職した友人数名にも聞いてきたので、それらを踏まえてお届けします!
この記事のゴール
- 大手各社(MBB/欧州系戦略/BIG4系/総合・IT系/日系大手/ブティック)の採用ポリシーと選考の型を俯瞰する。
- どこに時間を割くべきかが分かる“対策優先順位”を示す。
学生向けミニ用語辞典(まずはここから!)
- フィット面接:会社の価値観や働き方、チームとの**相性(fit)**を見る面接。過去の行動事例から、誠実さ・協働姿勢・再現性を確認する。
- 例:Q「意見が割れたチームをどうまとめた?」 → 結論/状況/あなたの行動/結果/学び、の順で端的に。
- PEI(行動事例面接:困難な状況でどう動き、何を学び、どう再現したかを問う):主にマッキンゼーで行われる行動事例面接。失敗・逆境・リーダー経験などを深掘りされる。
- 話し方の型=STAR:Situation(状況)→Task(役割)→Action(行動)→Result(結果)→Learn(学び)/Repeat(再現)。
- 例:「意見が対立した会議で調整役となり、相手のKPIを満たす代替案を提案→合意形成→以降も同手法を展開」
- 3失敗1成功(行動事例の弾:失敗3+成功1)ルール:行動事例の“在庫”として、失敗3本+成功1本を用意。学び→再現まで話せる形に整える。
- 失敗例の型:結論(ミス)→原因→是正→今ならこうする。
- 成功例の型:結論(成果)→鍵となる行動→再現条件。
- Interviewer-led/Candidate-led:ケース面接の進め方。前者は面接官が主導し設問が区切られる/後者は受験者が主導し仮説ドリブンで進める。
- GD(グループディスカッション):論点設計・役割分担・合意形成・時間管理を評価。「空気を整える」ふるまいも加点対象。
- BCF(Boston Career Forum/ボスキャリ):海外大・帰国生向けの採用イベント。MBB等が参加し特別ルートが用意されることがある。
1.MBB(マッキンゼー/BCG/ベイン)
採用ポリシー:問題解決力(ケース)×リーダーシップ(行動事例)×Drive(やり切る力)。ケース+フィット面接(価値観・働き方の相性)を複数ラウンド回し、総合力で評価。
選考の傾向: ES/オンライン適性 → ケース&フィット面接×複数(オフィスにより日英ミックス)→ 最終。海外大はBCF等のルートもあり。
ケース面接の型:
McKinsey:面接官主導(interviewer-led)+PEI(Personal Experience Interview)
BCG/Bain:候補者主導(candidate-led)中心。Bainはケース教材が公開されており、実務に近い定量が多い。
僕、BCGの本選考でオンライン適性→1次面接を1日で2回→2次面接でした。1次は日本語ケースでしたが、2次は一部英語でのディスカッションがありました。英語に切り替わった瞬間、結論が遅くなる癖が出て落ち着きを失いかけました……。
あるある。言語が変わっても結論→理由→検証の順は不変。メモに日本語で“骨子(論点)”を書き、口だけ英語にするのが安定するぞ。
ベインはケース→フィットの切り替えが速かったです。成功体験だけでなく、失敗→学び→再現まで聞かれました。(1次面接で落ちました、、)
PEI/フィットは1テーマを深堀りされる。STARで数字・役割・障害を入れて、“自分しか語れない一段深い因果”まで持っていけると強い。
あるあるの落とし穴:
フレームワークにに当てはめることに必死になり、**示唆(so what)**が薄い
対策優先度:
①ケースの“型”反復(毎日30分)
②PEI/フィットは3失敗1成功(行動事例の弾:失敗3+成功1)を用意
③日英スイッチの練習。
2.欧州系戦略(ローランド・ベルガー/アーサー・D・リトル/ATカーニー)
採用ポリシー:ケース比重は高め。リクルーティングデイやグループケースを通じ、協働×自走力(自分で論点を設計し、仮説→検証→方針に落とす力)を確認する色が強い。
選考の傾向: ES/(適性・筆記)→ 個人ケース→ グループケース→ 最終(マネジメント面接)という“1日完結型”が混ざることも。
ローランド・ベルガーのグループケースで、論点を広げすぎて時間切れになりました……。
最初の5分でGDの成功した状態の定義と評価軸を合意すべきだな。たとえば「3年で営業利益+50億」「初期投資◯億まで」みたいに。枠を決めればそれをベースに議論が走りだす。
「フィット面接」では何を見てるんですかね?
行動事例。対立の調整/困難の突破/率直なフィードバックの受け止めみたいなテーマで、あなたの役割と再現性を深掘りされる。型はSTAR(状況→役割→行動→結果→学び/再現)でOK。
あるあるの落とし穴:
GDで司会=主役だと思って話し続ける → 論点設計と合意形成が司会の役割。
対策優先度: (1,MBBと同じ)
①グループディスカッションの冒頭5分で成功状態の定義、評価軸、役割を合意する練習
②グループディスカッションの司会、時間管理+要約係、参加者など各役割の練習
3.BIG4系(デロイト/PwC/EY/KPMG)
採用ポリシー:協働性重視。職種によりケース/技術課題/プログラミング/長時間GDなど構成が多様。Web適性は共通で重い。
選考の傾向: ES→ Web適性 → 面接複数(職務適合+ケース)→ 最終。KPMGは自社レポート題材のオンラインケース+少人数ワークが特徴。EYはスタンダード/専門で入り口が分かれ、専門職種は技術評価の比重が上がる。
PwCはWeb適性後の面接テンポが速かったです。等身大の志望部門を言い切れたのが良かった気がします。
BIG4は“どの業界×課題×手法で価値を出すか”を考えておいた方が良いな。ケースは読み取り→整理→提案→発表の段取り力も採点されるぞ。
EYはロングGDで貢献量が見られました。要約役+時間管理を買って出ると安定しますね。
あるあるの落とし穴:
「どの部門でも活躍します」=解像度ゼロに見える/Web適性の足切りに引っかかる。
対策優先度:
①Web適性(玉手箱/SPI等)の早期着手
②志望部門×やりたい課題の具体化③段取り力(議事進行・まとめ・発表)の練習。
4.総合・IT大手(アクセンチュア)
採用ポリシー:変革の実行力。ビジネス/デジタル/テクノロジーのロール適合とGDの完成度を重視。
選考の傾向:ES → Web適性(玉手箱系が多い) → GD → 面接複数 → (職種別スキルテストの可能性) → 内定。
GDで無口→巻き返しは難しいので、最初に論点と役割をサッと提案するのが安定でした。僕はタイムキーパー+要約を兼務して評価が上がった実感があります。
アクセンチュアは実行フェーズの再現性を見てくる。自分のエピソードをBefore→Action→Afterで“どんな成果を得たか”まで言い切る必要があるな。
Webテ、各種面接などは対策さえすればある程度こなせるようになりますが、GDは当日予想外のことが起きる可能性高いですよね。友人ら、もしくは他企業で事前にロープレしておくのが吉です。
あるあるの落とし穴:
MBBに比べて志望者の大学が散らばるため、GDで発散する可能性がより高い/“IT嫌い”がにじむ(職種適合NG)。
対策優先度:
①GDの型(論点→仮説→ToDo)を固め、様々なタイプの人と同じグループディスカッションになっても対応できるようにする
②基礎IT/データ素養③再現性ある行動事例の準備。
5.日系大手(NRI)
採用ポリシー:課題設定力×対話の丁寧さ。企業研究の厚みと相互フィットを重視。
選考の傾向:ES/Web適性 → 面接複数(個人・場合によりGD)→ 必要に応じインターン → 最終。
面接で「なぜNRIか」を“案件類型×育成×出口”で語ったら、深掘りが具体になりました。
NRIは仮説検証の癖を見てきたな。「調査→示唆→反省→再現」を自分の言葉で回せるかがポイント。
あるあるの落とし穴:
日系だからと熱量だけで押し切る/相手の文脈を踏まえない逆質問。
対策優先度:
①企業研究の厚み(強み・案件レンジ)
②丁寧な対話
③地に足のついた志望先リスト
6.日系総合(アビーム、ベイカレント ほか)
採用ポリシー:配属の仕組み理解×素直さ。足切り(Web適性)を越えた上で、成長計画を語れるか。
選考の傾向:
アビーム:ES → SPI → 面接複数。コース選択と配属適合の確認が丁寧。
ベイカレント:ES/Web適性/録画面接 → ケース → 個人面接複数 →(インターン挟む場合あり)→ 最終。ワンプール配属の理解が鍵。
アビームは配属コースの狙いを明確に言うと、面談が一気に具体化しました。
逆に、ここがフワフワしているとダメだと思います。
ベイカレントは初期配属の幅が広い。入社後3年の成長計画を描いて、“どんな案件でどう伸びるか”を語ると良いな。
あるあるの落とし穴:
「何でもやります」で終わる/配属・育成の仕組みを知らない
対策優先度:
①配属/育成の理解
②ケースは素直×スピード
③成長ロードマップの言語化
Tips
ケース対策:毎日30〜60分でも、“型(結論→論点→定量→示唆)”の反復。友人らと面接官役・志望者役を交互に練習する。面接官役もやってみることで、論理の穴などに気づけるようになり、結果として自身のケース面接に活きてくる。
行動事例:1テーマにつき3失敗1成功(行動事例の弾:失敗3+成功1)の弾を用意。学び→再現の流れを磨く。
企業研究:四半期決算・プレス・代表インタビューからしっかりと企業の強み・特徴を理解する。
GD:論点設計、役割分担、タイムキープ、合意形成。“空気を整える人”は安定して高評価。
まとめ
同じ”コンサル”でも、見ているポイントが結構違いますね。
そう。“自分はどこで勝つのか”を決めて、対策の重みづけを変えること。これが最短ルートだ。
次回からは、各コンサルの選考をさらに深掘りしていきます!!